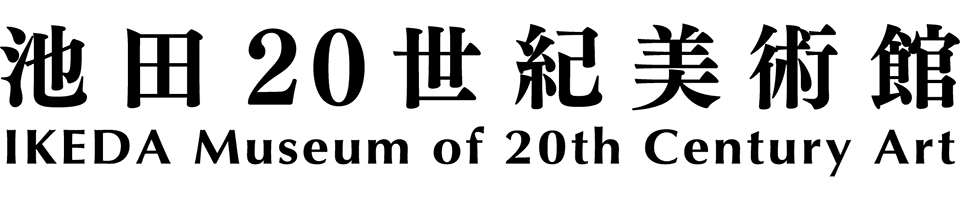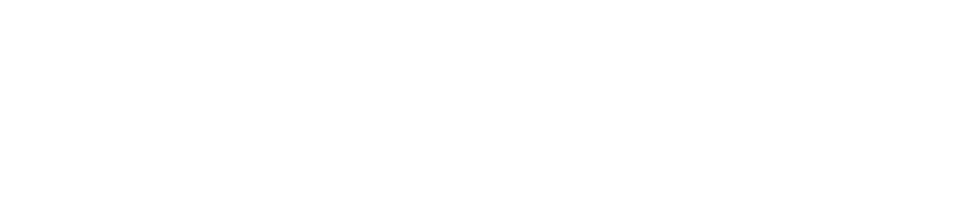- 2024.07.28
「神々の微笑・日本文化の根源を求めて 小灘一紀 古事記絵画展」ギャラリートーク開催いたしました(2024/07/27)
7月27日(土)、企画展「神々の微笑・日本文化の根源を求めて 小灘一紀 古事記絵画展」の展示会場でギャラリートークを開催いたしました。
小灘一紀先生、足利市立美術館次長・学芸員の江尻潔氏、羽曳野市議会議員の田仲基一氏、美術評論家で川崎市岡本太郎美術館館長の土方明司氏、元産経新聞特別記者兼編集長の安本寿久氏が参加しました。


当日は約90名が来場し、大盛況でした。伊藤館長の挨拶と当館の歴史紹介の後、小灘先生とゲストの方々の肩書や略歴が紹介されました。

続いて、小灘先生の挨拶と画家を目指した経緯が語られました。
小灘先生は20年以上にわたり古事記をテーマに作品を描いてきました。今回のサブタイトル『神々の微笑』は、芥川龍之介の小説から借用されたもので、異文化の衝突と融合をテーマにしています。キリスト教の宣教師が日本の神々と対峙しながら、日本文化を理解していく物語です。
先生が文学に触れたきっかけは叔父様の影響でした。父親を戦争で失い、母子家庭で育った先生は、内向的な性格でしたが、叔父様が文学や美術の話を通じて先生を導きました。その影響で芸術に目覚め、絵の教室に通い始めました。

高校では米子東高校の金畑実先生、京都では芝田米三先生に師事し、人体デッサンを学びました。大学では彫刻を学び、ルネサンス、バロックの古典美術からも学びましたが、次第に「日本人とは何か」「日本人にしか描けないものは何か」という問いに立ち返り、芥川の『神々の微笑』を再び読み返すことで、古事記を描くことに繋がりました。
美術評論家で岡本太郎美術館館長の土方氏が小灘先生と出会ったのは、2017年の日展の外部審査員を務めた際です。内閣総理大臣賞を受賞した「伊須気余理比売命」を強く推したのは、土方氏と千足伸行氏でした。

土方氏は、小灘先生の作品について「写実性とイマジネーションをうまく融合している」と評価しています。彼は、小灘先生の初期の自画像を例に挙げ、「内省的で幻想性が豊かであり、写実の力がある」と述べました。また、レンブラントなどのバロック芸術の影響を受け、出雲を描く際に独自の世界を生み出したことも指摘しています。彫刻の経験も写実性の高さに寄与していると述べました。
足柄市立美術館次長・学芸員の江尻潔氏は、「イザナギとイザナミの物語は、ギリシャ神話のオルフェウスを彷彿とさせる」と述べています。オルフェウスも愛する人との別れをテーマにしており、死んだ妻を追って冥界へ旅立ちますが、後ろを振り返らないという約束を破ってしまいます。

このように似た話があるものの、ギリシャ神話では神に逆らうと獣にされる恐ろしさがありますが、日本の神話ではそのようなことはありません。江尻氏は、「日本の神話は人間を否定せず、伸びやか」と評価しています。
羽曳野市市議会議員の田仲基一氏は、2006年から『オラトリオヤマトタケル』(作曲:三枝成彰氏、作詞:なかにし礼氏)の演奏に取り組んでいます。田仲氏は、小灘先生の「白鳥に生まれ変わる倭建命(ヤマトタケル)」を見て、イエス・キリストを連想したと述べています。

ヤマトタケルは、日本各地を平定する過程で多くの敵を討ち、穢れを負いました。病に倒れた後、白鳥となって飛び去ったと伝えられています。田仲氏は、広げた羽根がイエスの十字架を連想させるとし、ヤマトタケルとイエスの共通点として、神聖な血統、旅、試練、自己犠牲を挙げています。

また田仲氏は、「神話は事実でないとしても、民族としての真実がそこにある」と述べました。
元産経新聞の編集長で、現在はラジオ大阪の情報・報道番組の火曜日のアンカーマンを務める安本寿久氏は、2012年から産経新聞に「日本人の源流 神話を訪ねて」を連載し、その時に小灘先生のことを知りました。

安本氏は、「キリスト教や仏教と違って、偶像がなく、空(くう)なるものが日本の神様。それを絵画にするのはチャレンジングだ」と述べました。また、小灘先生の描く神々について、「男神はたくましく、女神は美しい。いずれも人間臭く、日本の神様の特徴をよく表している」と評価しています。

さらに、ローマやギリシャ神話では、神々が天地を創造するのに対し、日本の神話では、古事記の冒頭にも記されているように、まず自然や宇宙があり、それから神々が現れることを説明しました。
この話から再び小灘先生にマイクが渡り、先生はゴッホの話をしました。ゴッホは、「純度の高い芸術家を目指せ」「死んでから名を立てるぐらいの画家になれ」と先生を鼓舞してきた叔父様がよく引き合いに出した画家でした。ゴッホの日記を読むと、彼は浮世絵を観て感銘を受け、「日本の中には自然にも神が宿っている」と感じていたそうです。西洋の画家の中でゴッホだけが、目に見えない何か素晴らしいものが潜んでいることに気づいていたのです。

江尻氏もこの話を引き継ぎ、天地開闢の時に現れた「むすひのかみ」(産霊の神)が万物に命を与え、その成長・発展を助ける存在であると説明しました。ゴッホは色彩と形でその奥のエネルギーを感じ取り、渦巻などで表現していたのではないかと述べました。キリスト教文化においては、偶像として形ある神が崇拝されているため、目に見えない「根源的」なものの存在は薄れていきましたが、神道を信仰する日本には残り続けていました。江尻氏は、「ゴッホの悲劇的な人生も、日本に生まれていたらまた違っていたかもしれない」と締めくくりました。

岡本太郎美術館の館長である土方氏は、太郎もまたこのことを理解していたと説明します。岡本太郎は1930年から10年間パリで学びましたが、彼が渡仏したのは絵を学ぶためではなく、文化人類学の分野で著名な学者マルセル・モースから民俗学を学ぶためでした。
そして、それまで野蛮な文化として無視されていた縄文美術の価値を、太郎は土器を通して訴えました。昨今の縄文ブームですが、縄文時代の信仰も「古神道」で、この時代の人々は自然崇拝や精霊信仰を持ち、あらゆるものに神が宿ると信じていました。
『聡明なる混沌 何もない潔さ』という有名な太郎の言葉は、「日本の美意識の核にあると思う」と土方氏は言います。
仏教美術はありますが、神道美術はありません。形にはできるものではないからです。しかし岡本太郎は沖縄の久高島に渡り、石にも神が宿ることを知りました。つまり、これが日本の神道の在り方なのです。

最後に先生に今後の絵画制作について伺いました。先生の新しい作品は、日本神話の「非時香果(ときじくのかぐのこのみ)」に関するものだそうです。
第11代垂仁天皇は、不老長寿の実である「非時香果」を求めて田道間守(たじまもり)を常世の国に派遣しました。田道間守は10年の歳月をかけてこの実を見つけましたが、帰国したときにはすでに天皇は亡くなっていました。田道間守はその悲しみのあまり、天皇の墓前に実を捧げた後、自らも命を絶ちます。
先生は、この天皇が亡くなってしまった様子を描いているそうです。人間に必ず訪れる死をテーマにして描いている先生は、「この話もまた犠牲的でキリスト教に似ている」とお話されました。
最後に、世の中の矛盾において、いかに純粋に生きるかを全うした岡本太郎の話や、古事記を訳したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が、ある宮司の立ち居振る舞いを通じて、日本の根源にある信仰心や価値観を感じ取ったというエピソードを話され、トークショーを締めました。

様々な角度から小灘一紀作品に迫った非常に興味深いトークショーとなりました。
参加されたゲストの方々、全国各地からご来場された皆様には心から感謝いたします。ありがとうございます。